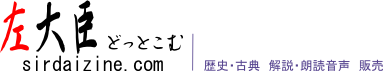徒然草
■【三日間限定】方丈記 全文朗読【無料ダウンロード】
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
兼好法師の『徒然草』は、清少納言の『枕草子』、
鴨長明の『方丈記』と並んで、日本三大随筆のひとつとされています。
全244段あり漢字を中心とした堅い文章と、仮名を中心としたやわらかな文章が混在した「和漢混淆文」で書かれています。
内容はバラエティ豊かです。
中心となる無常観や仏教のことだけでなく、芸術、政治・経済、医学、 自然や四季、ちょっとした逸話や豆知識など、 作者兼好法師の博覧強記っぷりがうかがえます。
「つれづれ」という言葉の意味は、暇つぶしに書いてみた、
ということですが、謙遜です。そんなテキトーなものではないのです。
実際にはいろいろな方面に話題を広げつつ、
人として、いかに生きるべきかという
深い問いが投げかけられております。
発表後100年くらいはほとんど注目されませんでしたが、
室町時代に禅僧の正徹という人が写本を書きます。
江戸時代に入って松尾芭蕉の師として知られる北村季吟などによって 注釈書が書かれると、庶民の間でさかんに読まれるようになりました。
「無常観」のとらえ方
『徒然草』が書かれたのは鎌倉時代末期。世の中が大きくゆれ動いていた時期です。
長きにわたった武士の支配に限界が見え、 やはり天皇が直接政治を見ないとダメだ ということで、後醍醐天皇が乗り出してきます。
しかし、天皇によるこの直接政治(建武の親政)もうまくいかず、 かえって事がややこしくなり、天皇家が二つに分裂。 以後約60年間にわたる南北朝の動乱へと突入します。
『徒然草』はそういう、
混沌とした時代背景の中で書かれました。
そのため、人の死、世の中のはかなさ(無常観)、
こういう話がとても多いです。
しかし、イジケたことは言ってません。はー世の中はかないなあ。 生きていてもツライだけだ、そんな泣き言を言ってるんじゃないんです。
逆に、無常をこそ、楽しもうという姿勢。
すべてのものは一定の状態に留まらない、 形あるものは亡びる、命あるものは死ぬ… しかし、だからこそ味わいがあるのだ。
…こういう前向きな考えに貫かれています。
たとえば、
あだし野の露消ゆるときなく、鳥部山の煙立ち去らでのみ、住み果つるならひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそ、いみじけれ。
もしあだし野の露が消えないように、鳥部山の煙がずっと留まっているように 人間がいつまでも行き続けたら、情緒も何もも無い。 人は死ぬからこそ、命は有限だからこそ、人生は面白いのだ、と。
前向きです。無常を前向きにとらえているんです。
このあたりが、同じ無常観というテーマを扱っていても
鴨長明の『方丈記』とはだいぶ趣が違います。
『徒然草』と比べると鴨長明の『方丈記』は世をはかなんだ、 後ろ向きな感じは否めません。
作者 兼好法師
作者の兼好法師は鎌倉時代末期~室町時代前期を生きた
歌人、隠遁者です。
俗名卜部兼好(うらべかねよし)。 卜部氏は代々朝廷に仕え、占いを執り行いました。 兼好の父兼顕は京都左京区の吉田神社の神職でした。
歌人としても有名で、頓阿・浄弁・慶運と並び、 「二条派の和歌四天王」と称されました。
また兼好法師は武家にも顔がききました。 足利尊氏・直義兄弟、その家臣の高師直など、 この時代を代表するそうそうたる顔ぶれと交流を持っていました。
兼好法師(卜部兼好)は時の後二条天皇に仕え、まずまずの
出世を重ねます。
それが何を思ったか、30歳前後で突然出家します。 出家の理由はまったくの不明です。
兼好が出家を思い立ったころ、秋の夕暮をみて詠んだ歌です。
そむきてはいかなる方にながめまし秋の夕べもうき世にぞうき
(もし出家したら、この秋の夕暮れはどんなふうに見えるのだろうか。
こんなつらい俗世間にいるからこそ、憂鬱な風景に見えるのだ。
出家したらこうスカッと気分が晴れて、この夕暮れの景色ももっとハツラツと
見えてくるのかもしれないなあ)
艶書代筆事件
『太平記』の中に兼好法師についての逸話があります。
幕府執事高師直(こうのもろのお)は、出雲・隠岐の守護・塩屋判官高貞(えんやはんがんたかさだ)の妻が大変な美人だという噂を耳にします。
ぬ!そんな美人なら何としてもモノにしたいということで、 名文家として知られる兼好に艶書(ラブレター)の代筆を頼みます。
しかし、塩屋判官の妻はとても貞淑な女性でした。 読みもせずに艶書をポイ捨てします。 師直はコケにされた形です。 怒りは女性に向かず、ラブレターを代筆した兼好に向きます。
「この役立たずめが!」
師直は兼好をさんざんに罵った、というお話です。
この話は江戸時代につくられた浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」の中に 取り入れられています。
序段
原文
つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
現代語訳
ヒマにまかせて一日中硯に向かって心に浮かんでは消えていくどうでもいいような事を何となく書き付けていると、あやしくもキチガイじみた感じがしてくる。
第一段
原文
いでや、この世に生れては、願はしかるべき事こそ多かめれ。
御門の御位はいともかしこし。竹の園生の末葉まで、人間の種ならぬぞ、やんごとなき。一の人の御有様はさらなり、ただ人も、舎人など賜はるきはは、ゆゆしと見ゆ。その子・うまごまでは、はふれにたれど、なほなまめかし。それより下つかたは、ほどにつけつつ、時にあひ、したり顔なるも、みづからはいみじと思ふらめど、いとくちおし。
法師ばかりうらやましからぬものはあらじ。「人には木の端のやうに思はるるよ」と清少納言が書けるも、げにさることぞかし。勢まうに、ののしりたるにつけて、いみじとは見えず。増賀ひじりのいひけんやうに、名聞ぐるしく、仏の御教にたがふらんとぞ覚ゆる。ひたふるの世捨て人は、なかなかあらまほしきかたもありなん。
人は、かたち・ありさまのすぐれたらんこそ、あらまほしかるべけれ。物うち言ひたる、聞きにくからず、愛敬ありて、言葉多からぬこそ、飽かず向はまほしけれ。めでたしと見る人の、心劣りせらるる本性見えんこそ、口をしかるべけれ。しな・かたちこそ生まれつきたらめ、心は、などか、賢きより賢きにも、移さば移らざらん。かたち・心ざまよき人も、才なく成りぬれば、品くだり、顔憎さげなる人にも立ちまじりて、かけずけおさるるこそ、本意なきわざなれ。
ありたき事は、まことしき文の道、作文、和歌、菅絃の道。また、有職に公事の方、人の鏡ならんこそいみじかるべけれ。手など拙からず走り書き、声をかくして拍子とり、いたましうするものから、下戸ならぬこそ、男はよけれ。
現代語訳
さてさて、この世に生まれたからには、「こういう者になりたい」と思う対象は、とても多いようだ。
帝の御位は言うも畏れ多い。帝の末の御子孫に至るまで、同じ人類では無いと言えるくらい尊いことだ。
帝についで最高位の身分である摂政・関白のご様子は、いまさら言うまでもない。それ以外の一般の貴族であっても、朝廷から警護役の舎人をつけていただく身分の方々などは、とても立派に見える。
その子・孫の代までは、落ちぶれたとしてもやはりどこかに気品が残っている。
それより身分の低い者どもは、身分や家柄に応じて、たまたま幸運がめぐってきて得意顔をしている者も、本人はいけてると思っているようだが、どうにもみっともない。
法師はちっとも羨ましいものではない。「人からは木の切れッ端のように思われることよ」と清少納言が書いているのも、なるほど、もっともだ。
権勢さかんで羽振りがよいといっても、それが良いこととは思われない。僧賀上人が言ったように、世間的な名声に心をくだくことは、仏の教えに反しているのじゃないかと思う。
しかし、一途に世を捨てて仏の道に打ちこんでいる人は、かえって、望ましいところもあるのだろう。
人は容貌や立ち居振る舞いがすぐれていることこそ望ましい。物を言っては聞き取りやすく、愛嬌があり、言葉数は多すぎない。こういう人とは長いつきあいをしていきたい。
いいなあと思っていた人が、意外にもいやしい本性を見せたときは、つまらないものだ。
品格や容貌は生まれつきだろう。だが心はいい方向にいい方向にと、引き上げられないことがあるだろうか。
容貌や気立てがすぐれた人であっても、才能がなくなると、卑しく憎憎しげな顔をした連中の間に立ちまじって、かつて持っていた良さをたちまちに失って堕落してしまう。その有様を見るのはとてもツライものだ。
人として望ましいのは本格的な学問を学び、漢詩を作り和歌を詠み音楽をかなで、また宮中の有職故実に通じ、儀式などの作法にも詳しく人の手本となることだ。こうなれば大したものだ。
うまい字でさらさらと走り書き、よい声で拍子を取り、酒をすすめられるとちょっと顔をしかめるのが、しかし全く飲めないというわけではない。こういう男こそ、すばらしい。