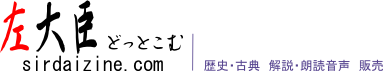伊勢物語
■【三日間限定】方丈記 全文朗読【無料ダウンロード】
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
「伊勢物語」は在原業平と思われる主人公「男」が元服してから死を予感するまでをつづった、一代記です。
といっても必ずしも主人公は史実の在原業平そのもの、というわけではなく、時には女や第三者が主人公になったり、物語的な飛躍があったりします。長短125段からなり(異本あり)、各章には必ず一首以上の歌があります。和歌の「詞書」のような感じで、歌が詠まれるに至った状況や物語が語られ、気持がもりあがった頂点で、歌が挿入される場合が多いです。
ただし『伊勢物語』の作中には在原業平という名前は出てきません。主人公に名前はなく、単に「男」と表記されています。
しかし主人公の歌に在原業平が詠んだ歌が多いこと、 作中で主人公が在原業平の異称「在五中将」と呼ばれていることから、「主人公=在原業平」ということはほぼ、間違いないと見られています。
【主要な章】
| 一 初冠 | 六 芥川 | 九 東下り |
| 二十三 筒井筒 | 六十三 つくも髪 | 六十五 在原なりける男 |
| 六十九 狩の使 | 八十二 渚の院 | 八十三 小野 |
| 八十七 布引の滝 | 百六 龍田川 | 百二十五 つひにゆく道 |
●『伊勢物語』でも特に有名で教科書に採られることが多い「初冠」「東下り」「芥川」など10章の音声+解説テキストを、無料でダウンロードできます。メールアドレスを入力し「ダウンロードする」ボタンを押してください。すぐにお手元のメールボックスに音声ファイルにアクセスできるurlが届きます。
声はこんな感じです。
●携帯電話のメールアドレスにはとどきません。パソコンのみの対応です。
●メールマガジンの読者サービスとして無料配布するものです。後日メールマガジン「左大臣の古典・歴史の名場面」をお送りさせていただきます。
●すべて無料で、不要な場合はいつでも解除できます。当無料ファイル送付とメルマガ配信以外にメールアドレスを使うことはありません。第三者に開示することはありません。
初冠
原文
むかし、男初冠して、奈良の京春日の里に、しるよしして、狩りに往にけり。 その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。この男かいまみてけり。 思ほえず、ふる里にいとはしたなくてありければ、心地まどひにけり。 男の、着たりける狩衣の裾を切りて、歌を書きてやる。 その男、信夫摺の狩衣をなむ着たりける。
春日野の若紫のすりごろも
しのぶの乱れ かぎりしられず
となむ 追ひつきて言ひやりける。ついでおもしろきことともや思ひけむ。
陸奥のしのぶもぢ 摺り誰ゆゑに
乱れそめにし 我ならなくに
といふ歌の心ばへなり。昔人は、かくいちはやき みやびをなむしける。
現代語訳
昔、ある男がいた。元服の儀式として初冠をすませて、奈良の都、春日の里の領地に狩をしに行った。
その里にとても美しく色香漂う姉妹が住んでいた。男はその姉妹を垣根越しに覗き見た。すると想像していたよりもはるかに美しい姉妹だった。古い都には似つかわしくないほど美しかったので、男は気持ちをかき乱されてしまった。
男は着ている狩衣の裾を切って、それに歌を書いて姉妹に送った。男はちょうど、しのぶ摺りの乱れ模様の狩衣を着ていた。
春日野の若紫の摺り衣の、その乱れた模様のように、私はあなた方のためにこんなにも心乱されてしまいました。
男は逃げ隠れようとする姉妹に追いついて、この歌を贈った。(または、「大人びた態度で歌を贈った」)うまいこと言ったとでも思ったであろうか。
この歌は「陸奥のしのぶもぢ 摺り誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに」という河原左大臣の歌をふまえたのである。
陸奥のしのぶ摺りの乱れ模様のように、こんなにも心乱されたのは誰のせいでしょうか。それは私自身のせいじゃない。まさにあなたのために、心乱されたんですという意味の歌である。
昔の人はこんなふうに、情熱にまかせて風流なことをしたものだ。
解説
元服式を終えたばかりの若者が、狩衣に身をまとい、領地のある奈良の春日の里を訪れ、うら若い姉妹に恋をする…『伊勢物語』全篇の巻頭にふさわしい、若々しい、さわやかな章です。
主人公「男」のモデルは在原業平(825-880)。 「色好み」の典型と言われます。当時の「色好み」という言葉は、しまりが無いなどの否定的な意味ではなく、恋の風情を愛する粋な人といった肯定的な意味でした。
なんと付き合った女性の数、三千七百三十三人と伝えられています。
825年、業平は平城天皇の子阿保親王の五男として生まれます。平城天皇はかの平安京を築いた桓武天皇の第一皇子です。
平安京遷都後16年目の810年、平城上皇はすでに弟の嵯峨天皇に位を譲って上皇となっていましたが、ふたたび帝位について、都を平安京から平城京に戻そうと画策します。薬子の変(平城大上天皇の変)です。
弟嵯峨天皇は、すぐに兄平城上皇の動きを察知。将軍坂上田村麻呂をもって、諸国の関所を封鎖させます。
結果、嵯峨上皇の動きは事前に封じられ、平城上皇に叛乱をたきつけたといわれる藤原薬子は毒をあおって自殺。その兄仲成は処刑されます。そして平城上皇は平城京で出家させられます。
平城上皇の第一皇子・阿保親王は、叛乱に加担したわけではないものの、やはり反逆者の息子ということで、ただではすまされませんでした。
阿保親王は太宰府に流され、以後14年間、太宰府ですごし、824年、父平城上皇が崩御したのに伴い、帰郷を許されます。その翌年生まれたのが業平です。
帰京したといってもやはり反逆者の家系ということで何かと肩身の狭い思いがあったようです。26年、行平、業平らの息子たちに在原の姓を賜り、臣籍に降下させました。
このようないきさつがあるので、業平にとって古都奈良は、特別な場所なのです。祖父平城上皇が都をもどそうとして戻せなかった「古郷」奈良。そこへ平城上皇の孫である業平が元服間もない頃訪れ、うら若い姉妹と恋をする…不思議な、歴史のつながりを感じないでしょうか。
芥川
原文
むかし、男ありけり。女のえ得まじかりるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗みいでて、いと暗きに来けり。芥川といふ河を率(ゐ)ていきければ、草の上に置きたりける露を、「かれは何ぞ」となむ男に問ひける。ゆく先おほく、夜もふけにければ、鬼ある所ともしらで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる倉に、女をば奥におし入れて、男、弓、胡簗(やなぐひ)を負ひて戸口にをり、はや夜も明けなむと思ひつつゐたりけるに、鬼はや一口に食ひてけり。「あなや」といひければ、神鳴るさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば率(ゐ)て来し女もなし。足ずりをして泣けどもかひなし。
白玉か何ぞと人の問ひし時つゆとこたへて消えなましものを
これは二条の后の、いとこの女御の御もとに、仕うまつるやうにてゐたまへりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひていでたりけるを、御兄(せうと)、堀川の大臣(おとど)、太郎国経の大納言、まだ下﨟にて、内裏(うち)へ参りたまふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、とどめてとりかへしたまうてけり。それをかく鬼とはいふなりけり。まだいと若うて、后のただにおはしける時とかや。
現代語訳
昔、男があった。手に入りそうもなかった女のもとに長年求婚し続けてきたのだが、とうとう盗み出して、たいへん暗い所に来た。芥川という河のあたりを女を連れて走っていったところ、草の上に露が降りているのを、「あれは何じゃ」と男にたずねた。
男はまだまだ逃げないといけないし、夜も更けてしまったので、そこが鬼のいる所とも知らないで、雷さえひどく鳴っていて雨もざあざあ降っているので、みすぼらしい倉に、女を奥に押し込んで、男は弓とやなぐいを背負って戸口で見張りしていた。
「早く夜が明ければいいのに」と思いながら見張りをしていたところ、鬼がたちまち女を一口で食ってしまった。「あれ」と叫んだのだが、雷が鳴っていて騒がしく、男は女の声を聞き取ることができなかった。
だんだん夜が明けてきた頃、見れば昨夜連れてきた女の姿が無い。男は地団太をして泣いたがどうしようもない。
白玉か何かだろうかと貴女が問われた時、「あれは露です」と答えて私も露のように消えてしまえばよかったのに。そうしていたらこんな悲しみを味わわないですんだのに。
この話は二条の后藤原高子が、いとこの女御の御もとにお仕えするようにして暮らしていらっしゃったのを、容貌が美しくいらっしゃったので、男が盗んで背負って飛び出したのを、御兄であらせられる堀川大臣藤原基経殿、その御長男国常の大納言らが、その時はまだ位も低くいらして、内裏へ参上された時、たいそう泣いている人がいるのを聞きつけて、引きとめて取り戻されたのだった。それを、こんなふうに鬼といったのだ。高子がまだたいそう若く、清和天皇のもとに入内する前のことであったとか。
解説
「芥川」という題で、教科書によく採り上げられる段です。業平・高子とおぼしき二人の物語のうちの一話です。高嶺の花の、高貴な女性のもとに男は通い、しかし身分違いの恋なので結婚など夢のまた夢です。でも愛しい。ええいもう、やってしまえ。
ばっと男は、女をかついで逃げ出します。はるかに逃げるわけです。芥川という川にかかった時、夜の闇の中に草の上の露がキラキラ光っているのが見え、「あれは何?真珠かしら」。「黙ってろ。今は先を急ぐ!」。
女は深窓の令嬢なので、露を知らないようです。もっともいくら深窓の令嬢でも庭のはっぱに降りてる露くらい見たことあるだろって気もしますが、ちょっとオーバーな表現なのかもしれません。
芥川は大坂の高槻市を流れる淀川の上流の川というのが一説ですが、御所から20キロも離れています。20キロも女しょって走っていくのは、ちょっと無理な感じです。または宮中のごみを捨てる川のことだという説もあります。
そこで振り出す雨。さらに雷も鳴り始めます。男は女をあばら屋の中に入れて、表で寝ずの番をしますが、朝になってみると、鬼に食われたように、いなくなっていました。
ああ、こんなことなら、あの時、あれは何ときかれた時、露と答えて露のように消えてしまうんだったと男は嘆くのでした。
「高子の兄たちが、取り返しに来たのだ」と付け足しのように書かれていますが、最初はほんとうに鬼に食われる説話だったのを、業平と高子の話としてふくらませたのかもしれません。なので前半と後半がちぐはぐな感じもしますが、同時に夢とうつつがまじりあったような不思議な味もあり、印象深い段です。
東下り
原文
むかし、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、あづまの方にすむべき国もとめにとてゆきけり。もとより友とする人、ひとりふたりしていきけり。道しれる人もなくて、まどひいきけり。三河の国八橋といふ所にいたりぬ。そこを八橋といひけるは、水ゆく河のくもでなれば、橋を八つわたせるによりてなむ、八橋といひける。その沢のほとりの木のかげにおりゐて、かれいひ食ひけり。その沢にかきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、「かきつばた、といふ五文字(いつもじ)を句のかみにすゑて、旅の心をよめ」といひければ、よめる。
から衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬるたびをしぞ思ふ
とよめりければ、みな人、かれいひの上に涙おとしてほとびにけり。
ゆきゆきて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、蔦かへでは茂り、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者(すぎやうざ)あひたり。「かかる道は、いかでかいまする」といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文かきてつく。
駿河なるうつの山辺のうつつにも夢にも人にあはぬなりけり
富士の山を見れば、五月のつごもりに、雪いと白うふれり。
時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿子まだらに雪のふるらむ
その山は、ここにたとへば、比叡の山を二十(はたち)ばかり重ねあげたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける。
なほゆきゆきて、武蔵の国と下つ総の国とのなかにいと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて、思ひやれば、かぎりなく遠くも来にけるかな、とわびあへるに、渡守、「はや船に乗れ、日も暮れぬ」といふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるをりしも、白き鳥の、はしとあしと赤き、鴫の大きさなる、水の上に遊びつつ魚(いを)を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見しらず。渡守に問ひければ、「これなむ都鳥」といふを聞きて、
名にしおはばいざ言問はむみやこどりわが思ふ人はありやなしやと
とよめりければ、船こぞりて泣きにけり。
現代語訳
昔、男がいた。その男、身を無用のものと思い詰めて、京にはおるまい。東国にすむべき国を求めようといって出発した。古くからの友人一人二人ひきつれて行った。道を知った人もいなくて、迷いつつ行った。三河の国八橋という所に至った。そこを八橋というのは、水が川となって蜘蛛の手のように八方にのびているので八つの橋をわたしたことから、八橋と言うのだった。その沢のほとりの木陰に降りて座って、乾飯を食べた。その沢にかきつばたがたいへん美しく咲いていた。それを見てある人が言うことには「かきつばた、という五文字を句の上に置いて、旅の心を詠め」と言ったので、詠んだ。
から衣をずっと着ていると衣の先がよれよれになるように、長年慣れ親しんできた妻を都に置いてきたので、はるばる旅をしているのだなあとしみじみ思う。
と詠んだところ、人々はみな乾飯の上に涙を落としたので乾飯が涙でふやけてしまった。
さらに行き、駿河の国に至った。宇津の山に至って、我々が踏み入ろうとする道はたいへん暗く細く蔦やかえでが茂り、何となく心細く、ひどい目にあうんじゃないかと思っているところに、修行者に出会った。
「どうしてこんな道をお通りなさる」と言うのを見れば、顔見知りだった。京に、あのお方の御もとにと思い、文を書きつける。
駿河の国の宇津の山辺を通っていくと、さびしくて人通りもありません。現にはもとより夢の中でさえあなたに会いできないのです。
富士山を見れば、もう五月末だというのに、雪がたいそう白く降っている。
雪がふるべき時期を知らない山。それはまさに富士だ。今がいつだと思って鹿の子の背中のようにまだら模様を成して雪が降っているのだろうか。
その山は、京でたとえると、比叡山を二十くらい重ね上げたほどのもので、形は塩尻(塩を生成するために海岸につくるすり鉢状の山)のようで、あることよ。
一行はなお進んでいき、武蔵の国と下総の国との境にたいそう大きな河がある。それをみすだ河という。その河のほとりに集まって座って、京の方を思いやれば、限りなく遠くへ来たものだなあとわびしい思いに暮れていたところ、渡守が「はやく船に乗れ。日が暮れてしまう」というので、船に乗って隅田川を渡ろうとしたところ、誰も彼もなんとなく侘しい気持ちになり、京に愛しい人がいないわけではない。そんな時、白い鳥の、くちびしと足が赤く、鴫くらいの大きさの鳥が水の上に遊びつつ魚を食っていた。京には見えない鳥なので、誰れその鳥の名を知らない。渡守に聞いたところ「これこそ都鳥」と言うのを聞いて、
その名も都鳥という名を持つお前に、いざきいてみよう。私の愛しい人はすこやかでいるか、どうかと。
と詠んだところ、船の上にいる人々はこぞって泣いたのだった。
解説
七段から十五段まで東下りの話が続きますが、中にもこの九段は総決算とも言うべき段で、教科書によく採り上げられ、有名です。
主人公が旅に出た動機は「身を用なきものと思ひなして」(わが身を無用のものと思いつめて)とあるだけで、よくわかりませんが、高子との道ならぬ恋の話の後に東下りの話がきているので、高子との関係がバレて追放された、という説が有力です。
また業平の兄行平が信濃守として赴任している時期があるので、ひょっとして業平も兄の任地に遊びに行って、その時に東国に興味を持ったのかもしれません。
三河→駿河→武蔵と、東海道に沿って歌枕の地が描かれます。
歌枕とは何でしょうか?
地名が、特定のイメージをかきたてて連想をさそうものです。この段でいえば、「かきつばた」をイメージさせる八橋。「夢かうつつか」という言葉を導く宇津の山。「夏の雪」というイメージの富士。「都鳥」の隅田川。現実の場所というよりも、イメージの中にある地名です。連想によってイメージをかきたてるものです。
旅の先々に歌枕を読み込む手法は、『伊勢物語』以後、「道行文」として、一種の型になっていきます。
松尾芭蕉の『おくのほそ道』も、道行文のスタイルにならったものです。『平家物語』には、一の谷の合戦で捕虜になった平重衡が京都から鎌倉へ護送される道行を描いた「海道下」という章がありますが、地名をリズミカルに詠みこんだ「道行文」スタイルになっています。
筒井筒
原文
むかし、ゐなかわたらひしける人の子ども、井のもとにいでて遊びけるを、おとなになりにければ、男も女もはぢかはしてありけれど、男はこの女をこそ得めと思ふ。女はこの男をと思ひつつ、親のあはすれども聞かでなむありける。
さて、このとなりの男のもとより、かくなむ、
筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹見ざるまに
女、返し、
くらべこしふりわけ髪も肩すぎぬ君ならずしてたれかあぐべき
などいひいひて、つひに本意のごとくあひにけり。
さて年ごろふるほどに、女、親なく、頼りなくなるままに、もろともにいふかひなくてあらむやはとて、河内の国、高安の郡に、いき通ふ所いできにけり。さりけれど、このもとの女、あしと思へるけしきもなくて、いだしやりければ、男、こと心ありてかかるにやあらむと思ひうたがひて、前栽のなかにかくれゐて、河内へいぬるかほにて見れば、この女、いとよう化粧じて、うちながめて、
風吹けば沖つしら浪たつた山夜半にや君がひとりこゆらむ
とよみけるを聞きて、かぎりなくかなしと思ひて、河内へもいかずなりにけり。
まれまれかの高安に来て見れば、はじめこそ心にくもつくりけれ、いまはうちとけて、手づから飯匙(いひがひ)とりて、笥子(けこ)のうつはものにもりけるを見て、心憂がりて、いかずなりにけり。さりければ、かの女、大和の方を見やりて、
君があたり見つつを居らむ生駒山雲なかくしそ雨はふるとも
といひて見いだすに、からうじて大和人、「来む」といへり。よろこびて待つに、たびたび過ぎぬれば、
君来むといひし夜ごとに過ぎぬれば頼まぬものの恋ひつつぞ経る
といひけれど、男すまずなりにけり。
現代語訳
昔、田舎暮らしの人の子供たちが、湧き水を木で囲んだもののもとに出て遊んでいたのだが、大人になったので男も女も互いに恥ずかしがっていた。しかし男はこの女とこそ結婚したい。女はこの男とこそと思いつつ、女の親はほかの者と結婚させようとするのだが、女はそれを聞き入れないでいた。
この隣の男のもとより、このように歌を送ってきた。
湧き水の筒にしるしをつけて測っていた私の背丈も、きっともう貴女を越してしまったことでしょう。貴女にお会いできないうちに。
女の返し、
長年貴方と背比べしてきた私の振分け髪も肩をすぎるほどに長くなりました。貴方以外の誰のために、この髪を結い上げるというのでしょうか。
などと言い合って、ついにもとからの願い通り、結婚した。
さて長年たつうちに、女は親が亡くなり、男の世話も満足にできなくなったので、男は一緒に貧乏生活になるのは嫌だと、河内の国高安の郡に行き通うもう一人の妻ができた。
そうではあったのだが、この最初の妻は、疑うそぶりも無く男を河内へ送り出すので、男は、浮気していると思って疑い、庭の植え込みに身をひそめて隠れ、河内へ行ったふりをして見ていると、この女、とても念入りに化粧をして、ぼんやり物思いに沈んで、
風が吹けば沖の白波が立つという名の龍田山を、今夜貴方は一人で越えるのでしょうか。
と詠むのを聞いて、どこまでも愛しく思って、河内へも通わなくなった。
たまたま例の高安に来てみれば、もう一人の妻は最初のうちは奥ゆかしく化粧していたのだが、今は遠慮が無さすぎで、侍女など使わずにみずから杓子をもって器に飯を盛るのを見て、男は嫌になってしまい、通わなくなった。なので女は男のいる大和の方角を眺め望んで、
貴方がいらっしゃるあたりを眺めていましょう。生駒山よ、雲であの人との間を隔ててしまわないでおくれ。たとえ雨が降ったとしても。
と歌を詠んで眺めていると、かろうじて大和にすむ男は「来る」と言った。女は喜んで待っていたが、何度もすっぽかされたので、
貴方が来るとおっしゃった夜ごとにすっぽかされて、もうあてにはしていないものの、恋しつつ時間が過ぎていくのです。
と女は詠んだが、男はもう通わなくなった。
解説
「筒井筒」などの題で教科書にはよく採り上げられます。「筒井つ」は丸く穴を掘った井戸。その井戸のところで、子供の頃ふたりで遊んでいたんですね。
さわやかな、子供時代の情景が浮かぶじゃないですか。その幼馴染の二人が年頃になって、念願かなって結婚しますが、男は女の親の経済力を頼りにしており、女の親が亡くなったらよそに女を作ってしまいます。
そればかりか、自分のことを少しも疑わない妻を、逆に疑うのです。こいつ、よそで男作ってるんじゃないかと。しかし男は妻の歌によってその優しい心を知り、よその女とは疎遠になるという話です。
女が男を思って詠んだ歌、あの人は今頃竜田山を夜に一人で越えているのかしらという歌は、『万葉集』の大伯皇女が、弟大津皇子を心配して詠んだ歌に通じる響きがあります。
二人行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ
ところで、この段の「男」は、あきらかに業平ではないです。男が女親の経済力をあてにしている点、京都ではなく河内と大和を拠点としている点から、業平とは別の、もっと低い身分の男だと読めます。
このように『伊勢物語』は必ずしも業平ばかりを追うわけではなく、時々寄り道をします。そこが、広がりが出て飽きないアクセントにもなっています。
つくも髪
原文
むかし、世心つける女、いかで心なさけあらむ男にあひ得てしがなと思へど、いひいでむもたよりなさに、まことならぬ夢がたりをす。子三人を呼びて語りけり。ふたりの子は、なさけなくいらへてやみぬ。三郎なりける子なむ、「よき御男ぞいで来む」とあはするに、この女、けしきいとよし。こと人はいとなさけなし。いかでこの在五中将にあはせてしがなと思ふ心あり。狩し歩(あり)きけるにいきあひて、道にて馬の口をとりて、「かうかうなむ思ふ」といひければ、あはれがりて、来て寝にけり。さてのち、男見えざりければ、女、男の家にいきてかいまみけるを、男ほのかに見て、
百年(ももとせ)に一年(ひととせ)たらぬつくも髪われを恋ふらしおもかげに見ゆ
とて、いで立つけしきを見て、うばら、からたちにかかりて、家にきてうちふせり。男、かの女のせしやうに、忍びて立てりて見れば、女嘆きて寝とて、
さむしろに衣かたしき今宵もや恋しき人にあはでのみ寝む
とよみけるを、男、あはれと思ひて、その夜は寝にけり、世の中の例として、思ふをば思ひ、思はぬをば思はぬものを、この人は思ふをも、思はぬをも、けぢめ見せぬ心なむありける。
現代語訳
昔、いい男と男女の関係になりたいと思っていた女が、どうにかして情の深い男と一緒になりたいものだと思っていたが、言い出すついでも無かったので、嘘の夢語りをする。
子供三人を呼んで語った。二人の子はそっけなく答えて終わった。三男であった子が、「よい殿方があらわれるでしょう」と話をあわせたので、この女はたいそう機嫌がよくなった。三男は思った。他の人はとても情が深いなどと言えない。どうにかして、例の在五中将と母を逢せてやりたいと心に思っていた。
在五中将が狩をしてまわっている所に三男は行き合って、道で馬の口をひきとどめて「こういうふうに、貴方をお慕いしています」と言ったところ、在五中将は深い情を感じて、女の家に来て寝たのだった。さてその後、男の訪れも絶えてしまったので、女は男の家に行って物の隙間から覗いてみると、男はちらっと女の姿を見て、
あと一歳で百歳という九十九歳のおばあさんが、私を恋い慕っているらしい。その姿が幻に見える。
と言って、女の家に出発する様子を見て、女は茨、からたちが引っ掛かるのも構わず、自分に家に帰ってうち伏せていた。男は女がしたように、こっそりと訪ねて行って物の隙間から覗いて見れば、女は嘆いて寝ようとして、
筵に衣の片方の袖だけをして、私は恋しい人に逢うこともなく、今夜も一人さびしく寝るのでしょうか。
と詠んだのを、男は哀れに思って、その夜は一緒に寝たのだった。男女の間の常として、自分を思う相手を思い、思わない相手を思わないものだが、この人は自分を思う相手も、思わない相手も、わけへだてなく扱う心を持っていたのだった。
解説
この段ではじめて主人公が「在五中将」と呼ばれます。この段の女は、三人の成人した息子があり、けっこうな年です。しかしさすがに「つくも髪」はおおげさで、出産する年齢が低かった時代の話なので、40前後ではないでしょうか。
ちなみに「つくも髪」は白髪のことですが、「九十九」と書いて、「百」につぐという意味でつくもと読みます。また「百」の漢字から上の「一」を抜かすと「白」となるので、白髪頭のことも意味します。
そういう女が、いい殿方とお会いしたいわという気持ちを持っています。息子たちが、誰かいい人紹介してくれないかしらとも思いますが、さすがに息子たちにハッキリは頼めないので、夢の話として息子たちに語ります。
「母は変な夢を見ました。素敵な殿方が私をかつぎあげて、さらっていくのです。これはどんな意味かしら」あきれる息子たち。
母上は、この年で、まだお盛んなのかと。しかし三男は母に話をあわせてやります。「母上、きっといい殿方があらわれますよ。噂の在五中将などは最高ですね」「それこそ最高だわ!」喜ぶ母をさらに喜ばせようと、三男は業平と母の仲立ちをします。
三男の手引きで業平はこの女と一晩をともにします。しかし、続けては通ってきません。女は、「ああ、もどかしい。業平さま業平さま」はしたなくも訪ねていき、垣根の向うから業平をのぞき見ます。
垣根の向うからのぞき見るのは男が女に対してやることです。それを女から男をのぞくのは異常な事態です。業平が縁側にでもいたでしょうか。
ふと見ると、女がくねくねとしなを作って、こっちを覗いている。まいったなあ。やなもの見ちゃった。そこで業平はそのちら見した姿を、「幻」だったとして歌を詠みます。白髪頭のバアさんが私をしたっているようだ。幻にその老女が出てきた。
万葉の昔より、幻の中に人の姿が出てくるのは、その人から強く思われている証拠、という考えがありました。だから、業平は目の前にちら見した老女の姿を「幻」として、老女が私のことを強く思っているようだと歌に詠んだのです。
「ああ!そんなふうに見られていたなんて!」女はさすがにショックで飛んで帰り、孤独をかみしめて、寝込んでしまいます。「さむしろに」と、孤独をかみしめる歌を詠んで。男はさすがに哀れになって、また、女と寝たという話です。
この女の歌は『古今集』にある詠み人知らずの歌「さむしろに衣かたしき今宵もや我を待つらむ宇治の橋姫」をふまえます。
狭いむしろの上に衣の片方だけをしいて、今宵も私を待っているのだろうか宇治の橋姫は。宇治の橋姫は宇治橋の守り神で、この詠み人知らずの歌は相手の女を、宇治の橋姫になぞらえています。
在原なりける男
原文
むかし、おほやけ思してつかうたまふ女の、色ゆるされたるありけり。大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女がたゆるされたりければ、女のある所に来てむかひをりければ、女、「いとかたはなり。身も亡びなむ、かくなせそ」といひければ、
思ふにはしのぶることぞまけにけるあふにしかへばさもあらばあれ
といひて曹司におりたまへれば、例の、このみ曹司には、人の見るをもしらでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。されば、なにの、よきこと、と思ひて、いきかよひければ、みな人聞きて笑ひけり。つとめて主殿司(とのもづかさ)の見るに、沓はとりて、奥になげ入れてのぼりぬ。
かくかたはにしつつありわたるに、身もいたづらになりぬべければ、つひに亡びぬべし、とて、この男、「いかにせむ、わがかかる心やめたまへ」と仏神にも申しけれど、いやまさりにのみおぼえつつ、なほわりなく恋しうのみおぼえければ、陰陽師、神巫(かむなぎ)よびて、恋せじといふ祓への具してなむいきける。祓へけるままに、いとど悲しきこと数まさりて、ありしよりけに恋しくのみおぼえければ、
恋せじとみたらし河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな
といひてなむいにける。
この帝は、顔かたちよくおはしまして、仏の御名を御心に入れて、御声はいと尊くて申したまふを聞きて、女はいたう泣きけり。「かかる君に仕うまつらで、宿世つたなく、悲しきこと、この男にほだされて」とてなむ泣きける。
かかるほどに、帝聞しめしつけて、この男をば流しつかはしてければ、この女のいとこの御身所、女をばまかでさせて、蔵にこめてしをりたまうければ、蔵にこもりて泣く。
あまの刈る藻にすむ虫のわれからと音をこそ泣かめ世をば恨みじ
と泣きをれば、この男、人の国より夜ごとに来つつ、笛をいとおもしろく吹きて、声はをかしうてぞ、あはれにうたひける。かかれば、この女は蔵にこもりながら、それにぞあなるとは聞けど、あひ見るべきにもあらでなむありける。
さりともと思ふらむこそ悲しけれあるにもあらぬ身をしらずして
と思ひをり。男は、女しあはねば、かくし歩きつつ、人の国に歩きて、かくうたう。
いたづらにゆきては来ぬるものゆゑに見まくほしさにいざなはれつつ
水の尾の御時なるべし。大御息所も染殿の后なり。五条の后とも。
現代語訳
むかし、帝がお心をかけて召し使われている女で、禁色を許された女があった。帝の生母、大御息所としていらっしゃる方の従妹であった。宮中の殿上の間に仕えていた在原という男で、まだたいそう若いのを、この女は互いに知り合うようになってしまった。男は、女房の局に出入りすることを許されていたので、女のいる所に来て向かい合ってじっと座っていたところ、女、「こんなことは、まともじゃありません。ばれたら身の破滅です。やめてください」と言ったので、
思う心の前に、しのぶ心は負けてしまいました。貴女に逢うためなら、どうなったってかまいません。
といって女が部屋に下がると、例の部屋には男が、人目があるのも知らないで上って座っている。こんな調子だったので女は気を病んで里へ行く。
すると男は何が悪いことがあるか。むしろいいことだと思い、女の里へ行き通うので、人は皆笑った。早朝、宮中警護の主殿司が見たところ、こっそり宮中に帰ってきた男は沓を脱いで奥にしまいこんで、そのまま殿上に上がるのだった。
このように普通でないことをしながらも、男は過ごしていたが、こんなことをしていてはいずれ官職も失い、ダメになってしまう。最後には破滅が待っているだろうと、この男は「どうしよう、私のこのような心をやめさせてください」と神仏に祈り申し上げた。気持ちは増しに増すのを感じながら、なおどうしようも無く恋しさばかりを感じていたので、陰陽師や巫女を呼んで恋をしないという払えの道具を持って、罪を流すために河原に行った。
お祓いの儀式をするにつれて、いよいよ悲しい気持ちが大きくなってきて、以前よりもいっそう恋しい気持ちばかり感じられるので、
もう恋などしないようにと御手洗川でみそぎをしたのですが、神はその願いをお聞き入れにならないようですね。
と歌を詠んで帰っていった。
この帝(清和天皇)は顔もお姿もうるわしく、仏の御名を御心に深くこめて、御声はたいそう尊く、お言葉をおっしゃるのを聞いて、女はひどく泣いた。「このような素晴らしい君にお仕えしないで、前世からの縁が悪く、悲しいこと。このような男の情に引かれるのは」と、泣いた。
こうしているうちに、帝が事の次第をお知りになり、この男を左遷なさったので、この女の従妹の大御息所(天皇の生母)が、女を宮中から退出させて、蔵にとじこめて折檻なされば、女は蔵にこもって泣く。
海女の刈る藻にすむ虫である割れ殻。そのわれからという言葉のように私の身から出た不祥事と思って泣きましょう。あのお方との仲を恨みには思いますまい。
と泣いていると、この男は地方から毎夜訪ねて来ては、笛をたいそう面白く吹いて、声は美しく、あわれ深く歌うのだった。なのでこの女は蔵にこもりながら、男が笛を吹いているに違いないとは聞くけれど、顔をあわせることもできずにいた。
あの方はまだ私に会えるかもと思っていることでしょう。それが悲しいのです。私がこんな生きているとも死んでいるともいえない身であるのを知らないで。
と女は思っていた。男は女に会えないので、このように歩きまわり、流された地に戻っては、このように歌う。
いつも空しく行っては帰ってきてしまうのだが、だからこそ逢いたい気持ちに誘われてまた出かけていってしまうのだ。
清和天皇の御時のことであろう。清和天皇生母の大御息所は染殿后(そめどののきさき)ともいわれた方で、五条の后とも伝えられる。
解説
四段・五段などと同じく、業平と高子の関係を語った章段です。ただし実際の業平と高子には17歳も年の差があります。
たとえば業平が35歳の時、高子は18歳です。しかしこの段では高子がすでに清和天皇に入内しているのに業平は若者のように描かれており、実際の業平と高子とは違う設定になっています。
当人たちにもどうにもコントロールできない情念のままに、破滅へとつきすすむ男女の姿。歌を一首重ねるごとに、二人の関係は深みにはまっていくのです。理性ではどうにもならない、何かに突き動かされるように。
最初は男から女への求婚だったものが、男は自分の感情をどうにも抑えられなくなります。神よ、この恋心を止めてくださいと御手洗川で禊までしたのに、どうにもならず、ますます恋い慕う気持ちはつのります。
一方女は、こんなすばらしい天皇(清和天皇)に私はお仕えしているのに、この男の情にほだされてと、男に心惹かれていく自分に罪悪感を抱き、しかしどうにもならない感情を歌に託します。
とうとう二人の関係は帝の知るところとなり、男は流罪となり、女は蔵に押し込められます。ところで九段などの「東下り」の話を、男が高子との関係がバレて、流罪になった果ての出来事だと考えることもできそうです。
また歌の中に「われから」が出てきます。「われから」は海藻のところにすむ節足動物でこの歌では「私から」の意味として使われています。和歌にはよく出てくる生き物です。
後半は、蔵に閉じ込められているところへ男が毎夜訪ねてくるとか、笛をふくとか、ありえない話が続きますが、こういう飛躍も歌物語の面白さの一つでしょう。
狩の使
原文
むかし、男ありけり。その男、伊勢の国に狩の使にいきけるに、かの伊勢の斎宮(いつきのみや)なりける人の親、「つねの使よりは、この人よくいたはれ」といひやれりければ、親の言なりければ、いとねむごろにいたはりけり。朝には狩にいだしたててやり、夕さりはかへりつつ、そこに来させけり。かくて、ねむごろにいたつきけり。二日といふ夜、男、われて「あはむ」といふ。女もはた、いとあはじとも思へらず。されど、人目しげければ、えあはず。使ざねとある人なれば、遠くも宿さず。女のねや近くありければ、女、人をしづめて、子一つばかりに、男のもとに来たりけり。男はた、寝られざりければ、外の方を見いだしてふせるに、月のおぼろなるに、小さき童をさきに立てて人立てり。男いとうれしくて、わが寝る所に???(ゐ)て入りて、子一つより丑三つまであるに、まだ何ごとも語らはぬにかへりにけり。男いとかなしくて、寝ずなりにけり。つとめて、いぶかしけれど、わが人をやるべきにしあらねば、いと心もとなくて待ちをれば、明けはなれてしばしあるに、女のもとより、詞はなくて、
君や来しわれやゆきけむおもほえず夢かうつつか寝てかさめてか
男、いといたう泣きてよめる、
かきくらす心の闇にまどひにき夢うつつとは今宵さだめよ
とよみてやりて、狩にいでぬ。野に歩けど、心はそらにて、今宵だに人しづめて、いととくあはむと思ふに、国の守、斎宮の頭(かみ)かけたる、狩の使ありと聞きて、夜ひと夜、酒飲みしければ、もはらあひごともえせで、明けば尾張の国へたちなむとすれば、男も人しれず血の涙を流せど、えあはず。夜やうやう明けむとするほどに、女がたよりいだす盃のさらに、歌を書きていだしたり。取りて見れば、
かち人の渡れど濡れぬえにしあれば
と書きて末はなし。その盃のさらに続松の炭して、歌の末を書きつぐ。
またあふ坂の関はこえなむ
とて、明くれば尾張の国へこえにけり。斎宮は水の尾の御時、文徳天皇の御女、惟喬(これたか)の親王(みこ)の妹。
現代語訳
昔、男がいた。その男が伊勢の国に狩りの勅使として派遣されたところ、かの伊勢の斎宮である人の親が、「いつもの使いよりは、この人をよく労わりなさい」と言い送ったので、親の言葉なので、たいそう心をこめて労わっていた。
朝は狩りに送り出してやり、夕方には帰ってくると斎宮の御在所に来させる。こうして、仲睦まじくいい関係になった。最初に男が泊まってから二日目の夜、男は強いて「逢おう」と言う。女もまた、ぜったいに逢うまいとは思わない。しかし人目が多いので、逢うことができない。
正使の人なので、遠く宿をとっているわけではない。女のねやの近くにいたので、女は周囲が寝静まるのを待って、子一つ(午後11時から11時半)に男のもとにやってきた。男はまた、寝られないので外のほうを見て横になっていたところ、月のおぼろな時分に、小さい童を先に立てて人が立っている。
男はたいそう嬉しくて、自分が寝る所に女をひっぱっていって布団に入って、子一つ(午後11時から11時半)から丑三つ(午前2時から2時半)まであるのに、まだ何も話さないうちに女は帰っていった。男はたいそう悲しくて、寝ないでいた。早朝、不審だったが、自分のほうから女のもとに使を出すのもはばかられるので、たいそう頼りない気持ちで待っていると、夜が明けてしばしたった頃、女のもとから詞はなく、
貴方がいらしたのでしょうか。私が行ったのでしょうか。私にはわかりません。夢なのか現なのか。寝ていたのか覚めていたのか。
男はひどく泣いて詠んだ。
悲しみに真っ暗になった私の心は、闇の中に迷っていました。夢か現かは、今夜決めてください。
と詠み送って、狩に出た。野を歩いても、心はうつろで、せめて今夜だけでも周囲が寝静まるのを待って一刻も早い時間に会おうと思っていたところ、伊勢守と斎宮寮頭を兼任している男が、狩の使が赴任したと聞いて一晩酒宴を開いたので、いっこうに逢いに行くこともできず、夜が明ければ尾張の国へ出発する予定なので、男も血のような涙を流したが、逢えなかった。夜が次第に明けてくるころ、女の住まいより送ってきた盃の皿に、歌を書いてよこしてきた。取って見ると、
徒歩で河を渡る人ですら衣の裾が濡れないくらいの、私と貴方の縁はそんな浅いものでしたので…
と書いて、下の句はない。男はその盃の皿に松明の燃え残りの炭で、下の句を書き足す。
…だからまた、逢坂の関を越えて、貴女に逢いに来ましょう。
と詠んで、夜が明ければ尾張の国へ山を越えて行った。この斎宮は清和天皇の御時、文徳天皇の御娘、惟喬の親王の妹、恬子内親王である。
解説
伊勢斎宮の話は、四段五段などの藤原高子の話と並び、『伊勢物語』の主要な筋の一つです。『伊勢物語』という題名のゆらいとなっているとも言われます。
しかも、男の相手は皇族です。そしてアマテラスオオミカミに奉仕する絶対不可侵の、聖なる存在たる伊勢の斎宮です。高子の場合よりも、さらに犯しがたさが、大きいのです。
さらに女のほうから男を訪ねていっていること。「子一つより丑三つまで」過ごした時間が具体的に描かれていること。四時間もいっしょにいることなど、描写が生々しいです。とはいえ、二人の間に密通の事実はなかったようです。
「まだ何事も語はぬにかへりにけり」…「語る」は男女が語り合うから、関係を持つことを意味するので、何事も語らってないといっているので、事実はなかったと見るべきでしょう。とはいえ、一夜をすごした後の歌のやり取りは、事実があったような、なかったような、どちらとも取れる形になっています。
すべてが夢の中の出来事のように、もやに包まれた感じがあります。
伊勢の斎宮
「伊勢の斎宮」は「伊勢の斎宮(いつきのみや)」ともいい、伊勢神宮に奉仕した内親王、もしくは女王(じょおう)のことです。内親王とは皇族の女子のうち親王宣下を受けた者で、女王は親王宣下を受けていないものです。
現在の皇室典範では皇族に女子が生まれると何の手続きもなく「内親王」とされますが、かつては「親王宣下」を受けないと、親王や内親王にはなれませんでした。まあ、ざっくりと、「皇室の女子が伊勢神宮に奉仕したもの」と考えてください。
伊勢の斎宮の歴史をいえば10代崇神天皇の御世に、それまで天照大御神を皇居でお祀りしていたのを、畏れ多いこととして倭笠縫村(かさぬいむら)に神殿を建てて遷し、崇神天皇の皇女豊鋤入姫命(とよすきいりひめのみこと)に奉仕させたことに始まり、7世紀後半天武・文武朝に制度が整いました。
天皇が即位すると占いにより内親王、内親王がいない場合は女王から斎宮が選らばれ、まず宮中の初斎院(しょさいいん)で、次に都の外の野々宮で身を清め、三年の後に伊勢神宮に向かいました。斎宮の御所には500人もの役人や侍女が奉仕しました。斎宮を下るのは、天皇が崩御か譲位した時、または斎宮の母親が病気の時に限られました。
後醍醐天皇の時、南北朝の動乱で伊勢に向かうことができず、そのまま廃止されました。文学作品にも伊勢の斎宮は多く描かれ『源氏物語』で六条御息所が伊勢の斎宮として下る際、京都嵯峨野の野々宮神社に光源氏が見送る場面が特に有名です。
狩の使い
「狩の使い」とは、朝廷の宴会などで使う鳥獣を狩るために諸国に派遣された勅使です。多くは五位の蔵人(くろうど。宮中のことを扱う役人)が、これにあたりました。
渚の院
原文
むかし、惟喬の親王と申すみこおはしましけり。山崎のあなたに、水無瀬といふ所に、宮ありけり。年ごとの桜の花ざかりには、その宮へなむおはしましける。その時、右の馬の頭なりける人を、常に率ておはしましけり。時世経て久しくなりにければ、その人の名を忘れにけり。狩はねむごろにもせで、酒をのみ飲みつつ、やまと歌にかかれりけり。いま狩する交野の渚の家、その院の桜、ことにおもしろし。その木のもとにおりゐて、枝を折りて、かざしにさして、かみ、なか、しも、みな歌よみけり。馬の頭なりける人のよめる。
世の中にたえてさくらのなかりせば春の心はのどけからまし
となむよみたりける。また人の歌、
散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世になにか久しかるべき
とて、その木のもとは立ちてかへるに日暮になりぬ。御供なる人、酒をもたせて、野よりいで来たり。この酒を飲みてむとて、よき所を求めゆくに、天の河といふ所にいたりぬ。親王に馬の頭、大御酒(おほみき)まゐる。親王ののたまひける、「交野を狩りて、天の河のほとりにいたる、を題にて、歌よみて盃はさせ」とのたまうければ、かの馬の頭よみて奉りける。
狩りくらしたなばたつめに宿からむ天の河原にわれは来にけり
親王、歌をかへすがへす誦じたまうて、返しえしたまはず。紀の有常、御供に仕うまつれり。それが返し、
ひととせにひとたび来ます君待てば宿かす人もあらじとぞ思ふ
かへりて宮に入らせたまひぬ。夜ふくるまで酒飲み、物語して、あるじの親王、酔ひて入りたまひなむとす。十一日の月もかくれなむとすれば、かの馬の頭のよめる。
あかなくにまだきも月のかくるるか山の端にげて入れずもあらなむ
親王にかはりたてまつりて、紀の有常、
おしなべて峰もたひらになりななむ山の端なくは月も入らじを
現代語訳
昔、惟喬の親王と申し上げる皇子がいらっしゃった。山崎の向う、水無瀬という所に、親王の離宮があった。毎年の桜の花ざかりには、その離宮へいらっしゃる。その時、右の馬寮の長官であった人を、いつもつれていらっしゃった。今までに長い時が経ったので、その人の名は忘れてしまった。鷹狩は熱心にもしないで、酒をひたすら飲みつつ、和歌に取りかかった。今、鷹狩をする交野の渚の家、その院の桜、格別に趣深い。その木の下に馬を下りて座って、枝を折って、かんざしに挿して、身分の高い人も中ぐらいの人も低い人も、皆歌を詠んだ。馬の頭であった人が詠んだ。
世の中に桜がまったく無かったら、桜の散るのを心配する必要も無くなり、人々の春の心はのどかなものになるでしょう。
また別の人の歌、
散るからこそ桜はこんなにもめでたく思えるのだ。この辛い世の中に、いつまでも変わらないものなどあろうか。無い。すべてのものは移りすぎて行く。
と詠んで、その木の下から水無瀬の離宮に戻って日が暮れた。お供の人が酒を持たせて、野から出てきた。この酒を飲もうということで、いい場所を探していったところ、天の河という所に至った。親王に馬の頭がお酒を差し上げる。
親王がおっしゃった。「交野を狩りして天の河のほとるにいたる、を題にして、歌を詠んで盃を差しなさい」とおっしゃったので、かの馬の頭が詠んで献上した。
狩りをしているうちに日が暮れてしました。七夕の織女に宿を借りましょう。天の河原に私は来たのです。
親王は、歌を返す返す唱えられて、返歌がおできにならない。紀有常が御供に仕えていた。それが返し、
一年に一回来る恋人を織女は待っているのですから、宿を貸してはくれないでしょう。
親王一行は帰って、水無瀬の離宮にお入りになった。夜が更けるまで酒を飲み物語して、主人である親王が、酔って寝所にお入りになろうとする。十一月の月も雲間に隠れようとしていたので、かの馬の頭が詠んだ。
まだ見足りないし飲み足りないのに、月は山の端に隠れてしまうのですか。いっそ山の端が逃げていって、月を隠れさせないようにしてほしいです。
親王にお代わり申して紀の有常が、
峰をならして平らにしてほしいです。山の端がなくなれば月も隠れられないですから。
解説
惟喬親王は文徳天皇第一皇子で、父天皇がことに寵愛しておられた親王でした。次期皇太子とも見られていましたが、惟喬親王の母は紀名虎の娘で藤原氏ではありませんでした。
対して第四皇子の惟仁(これひと)親王は、母が藤原良房の女あり後ろ盾は磐石です。藤原氏の強い後押しによって惟仁(これひと)親王が皇太子に立ち、清和天皇として即位しました。これが惟喬親王7歳の時です。
さらにその後、清和天皇と藤原高子との間に定明親王が誕生し、皇太子に立ちます。後の陽成天皇です。
ここに至り、惟喬親王の皇位継承の望みは完全に絶たれました。惟喬親王26歳の春でした。
皇位継承の望みを絶たれた惟喬親王はウックツした思いをまぎらわせるように、風流の遊びに没頭していきます。そんな惟喬親王のお側にいつもお仕えしていたのが在原業平です。業平は親王よりも19歳年上です。
惟喬親王は、大坂の水無瀬(大阪府島本町)に離宮を持っており、
毎年、花盛りの頃にはこの離宮に出かけていかれました。
親王の御幸ですから、業平のほかにもおおぜいのお供が
ぞろぞろと、つきそっていきます。
大坂の交野(かたの)で一行は狩を楽しみます。
狩もそうそうり切り上げ、酒を飲んでは、
では、そろそろ歌を詠もう。業平、期待しておるぞ
となります。
淀川のほとりは、桜が見事に咲き乱れていました。
人々は桜の枝を折り、かざしに挿して、ワイワイいっています。
そんな中、在原業平が詠みました。
世の中に 絶えて桜のなかりせば
春の心は のどけからまし
世の中に、桜が無くなってしまえば、
春の心はどんなにか、のんびりするだろうに。
(つまり、春は短い間、桜が咲く。だから今日はどこの桜。
明日はどこの桜。西に東に花見に走り、ソワソワする。
いっそ桜なんて無かったら、気分が落ち着くのだが)
また別の人が詠みました。
散ればこそいとど桜はめでたけれ
憂き世になにか久しかるべき
(散るからこそ、桜はすばらしいのだ。
この憂き世で、永遠なものなんて、あるだろうか。いやない)
その後、交野から淀川の支流天の川に入り、天の川という地名に
ことよせた歌を詠み、水無瀬の離宮に戻ってからも、
夜更けまで酒を飲んで、この楽しい夜が終わらないでほしいという意味の
歌を詠みあうのでした。
惟喬親王と業平はじめお供の人々との心温まる交流が感じられる段です。
この後、惟喬親王は29歳で貞観14年(872年)出家して洛北の小野に
隠棲し、小野宮と号しました。
小野
原文
むかし、水無瀬に通ひたまひし惟喬の親王、例の狩しにおはします供に、馬の頭なるおきな仕うまつれり。日ごろ経て、宮にかへりたまうけり。御おくりしてとくいなむと思ふに、大御酒たまひ、禄たまはむとて、つかはさざりけり。この馬の頭、心もとながりて、
枕とて草ひきむすぶこともせじ秋の夜とだにたのまれなくに
とよみける。
時は三月(やよひ)のつごもりなりけり。親王おほとのごもらで明かしたまうてけり。かくしつつ仕うまつりけるを、思ひのほかに、御ぐしおろしたまうてけり。正月(むつき)におがみたてまつらむとて、小野にまうでたるに、比叡の山のふもとなれば、雪い高し。しひて御室(みむろ)にまうでておがみたてまつるに、つれづれといともの悲しくておはしましければ、やや久しくさぶらひて、いにしへのことなど思ひいで聞えけり。さてもさぶらひてしがなと思へど、おほやけごとどもありければ、えさぶらはで、夕暮にかへるとて、
忘れては夢かとぞ思ふおもひきや雪ふみわけて君を見むとは
とてなむ泣く泣く来にける。
現代語訳
昔、水無瀬の離宮に通われた惟喬の親王が、いつもの鷹狩をしにおいでになる供に、馬の頭である老人が仕えていた。何日も経過して、親王は今日の御殿に戻られた。馬の頭はお送りしてすぐに立ち去ろうと思っていたところ、お酒をふるまわれ、褒美に絹などをくださろうということで、男を立ち去らせることを、なさらなかった。この馬の頭は心配になって、
枕として草を引き結んで旅寝なんてしませんよ。今は春ですから、秋の夜長を頼みにしてゆっくり休むこともできないのですから。短い春の夜は自宅でゆっくり休みたいものです。
と詠んだ。
時は三月の末であった。親王はお休みにもならないで夜をお明かしになった。このようにしつつお仕え申し上げていたのだが、思いもかけず、親王はご出家なさったのだ。次の正月に親王を拝み申し上げようと洛北の小野に参詣したところ、比叡山のふもとなので、雪がとても高く積もっている。強いて親王の居室に参詣して拝み申し上げたところ、何となくたいそうもの悲しくしていらっしゃるので、やや長い間ご一緒して、昔のことなど思い出してお話申し上げた。そのままお側にお仕えしていたいと思ったが、公務が山積みで、お仕えすることもできず、夕暮に帰るにあたって、
ふと現実を忘れ、今のことを夢かと思います。思いもしませんでした。雪を踏み分けて貴方を訪ねていくことになろうとは。
と詠んで泣く泣く都に帰ってきた。
解説
前半は前の段からの続きです。水無瀬での遊びの後、京都の館に戻ってきてからも、業平は惟喬親王に引き留められます。いいじゃないか。業平、もう一杯つきあえなどと言われたのでしょう。困りましたねえなどといいながら、結局付き合う業平。なんとも微笑ましい君臣の交わりですが、そのほほえましい前半があるだけに、後半の雪景色の悲劇性が、いっそう強調されます。
惟喬親王は父文徳天皇の寵愛篤い親王でしたが、母方が紀氏であり、皇太子に立つことができませんでした。母方に藤原氏を持つ第四皇子の惟仁親王が皇太子に立ち、清和天皇として即位します。その後、清和天皇と藤原高子との間に生まれた貞明親王が貞観10年(869年)皇太子に立ったことで、惟喬親王の皇位継承の望みは完全に絶たれました。時に惟喬親王26歳。
3年後の貞観4年(872年)惟喬親王は29歳にして洛北小野里に隠棲します。比叡山から吹き付ける吹雪。そこを、業平が、旧主を訪ねて行くのです。楽しかった水無瀬での狩、歌会、酒を飲んだこと。あの楽しかった時間を思うにつけ、京の雪の景色が、いっそう悲しく胸に迫るのです。
布引の滝
原文
むかし、男、津の国、菟原(うばら)の郡(こほり)、蘆屋の里にしるよしして、いきてすみけり。昔の歌に、
蘆の屋のなだのしほ焼きいとまなみつげの小櫛もささず来にけり
とよみけるぞ、この里をよみける。ここをなむ蘆屋のなだとはいひける。この男、なま宮づかへしければ、それをたよりにて、衛府の佐ども集り来にけり。この男のこのかみも衛府の督(かみ)なりけり。その家の前の海のほとりに、遊び歩きて、「いざ、この山のかみにありといふ布引の滝見にのぼらむ」といひて、のぼりて見るに、その滝、ものよりことなり。長さ二十丈、広さ五丈ばかりなる石のおもて、白絹に岩をつつめらむやうになむありける。さる滝のかみに、わらうだの大きさして、さしいでたる石あり。その石の上に走りかかる水は、小柑子(せうかうじ)、栗の大きさにてこぼれ落つ。そこなる人にみな滝の歌よます。かの衛府の督まづよむ。
わが世をば今日か明日かと待つかひの涙の滝といづれ高けむ
あるじ、次によむ。
ぬき乱る人かそあるらし白玉のまなくも散るか袖のせばきに
とよめりければ、かたへの人、笑ふことにやありけむ、この歌にめでてやみにけり。
かへり来る道とほくて、うせにし宮内卿もちよしが家の前来るに、日暮れぬ。やどりの方を見やれば、あまのいさり火多く見ゆるに、かのあるじの男よむ。
晴るる夜の星か河べの蛍かもわがすむかたのあまのたく火か
とよみて、家にかへり来ぬ。その夜、南の風吹きて、浪いと高し。つとめて、その家の女の子どもいでて、浮き海松(みる)の浪に寄せられたるひろひて、家の内にもて来ぬ。女方より、その海松を高杯にもりて、かしはをおほひていだしたる、かしはにかけり。
わたつみのかざしにさすといはふ藻も君がためにはをしまざりけり
ゐなかの人の歌にては、あまれりや、たらずや。
現代語訳
昔、男が津の国菟原の郡、蘆屋の里に知人がいて、行って住んでいた。昔の歌に、
蘆屋の灘の塩を焼いていて暇が無いので、黄楊の櫛もささずにあわてて飛んできましたよ。
と詠んだのは、この里を詠んだのだ。ここを、まさに蘆屋の灘と言ったのだ。この男、そう身分が高いわけでもなく形ばかりの宮仕えをしていたので、それを頼って衛府の佐どもが集まってきた。この男の兄も衛府の督(長官)であった。その家の前の海のほとりに、いろいろ景色を見てまわって、「さあ、この山の上にあるという布引の滝に上ってみようじゃないか」と言って、上ってみると、その滝は並の滝とは違っていた。長さは二十丈(60メートル)、広さは五丈(15メートル)ぐらいである石の面に滝が打ちつけてまるで白絹で岩を包んだようであった。
そんな滝の上のほうに、円い座布団の大きさをして、さし出した石がある。その石の上に走りかかる水は、小さい蜜柑、栗の大きさでこぼれ落ちる。そこにいた人に皆滝の歌をよませる。かの衛府の督がまず詠む。
「私の時代は今日来るか明日来るか」そう言って待っている甲斐もなく流れる私の涙の滝。私の涙の滝と、この滝と、どちらが高いだろう。
玉の緒を引き抜いて、玉を乱れ飛ばしている人があるのだろうか。真珠の玉のようなしぶきが絶え間なく散ることよ。それを受け止める私の袖は狭いのに。
と詠んだところ、傍らにいた人は、この素晴らしい歌に比べたら自分の歌などお笑い草だと思ったのか、この歌を素晴らしく思って歌を詠むことをやめてしまった。
家に帰ってくるまでの道は遠くて、亡くなった宮内庁の長官もちよしの家の前に来たら日が暮れた。家の方を見やれば、漁師の漁火が多く見えるのを、かの主人が詠んだ。
晴れた夜の星か、川辺の蛍だろうか、それとも私が住む家のあたりの漁師のたく漁火だろうか。
と詠んで、家に帰ってきた。
その夜、南風が吹いて波がたいそう高かった。早朝、その家の女の子供たちが家を出て浮き海松(みる 藻)が浪で陸地に寄せられたのを拾って、家の中に持って来た。女の居所のほうから、その海松を高盃にもって、その上に柏の葉をおおって差し出した。その柏に書いた。
海の神様が簪にさすために大切になさるという海藻ですが、貴方のために惜しみなく陸地に流れ寄せてくださいました。
田舎の人の歌としては、これで十分なのか、いまいちなのか。
解説
33段と同じく、津の国菟原の郡を舞台とした話です。このあたりには業平の父・阿保親王の領地があったようです。また業平の兄行平は具体的にはわからないものの、かつて津の国に事情があって流されたことがあり、在原氏にとってこの津の国は因縁深い場所なのです。
最初の歌は蘆屋の里の雰囲気を形づくる導入になっています。蘆の屋の灘の塩焼きいとまなみつげの小櫛もささず来にけり。意味は蘆屋の海女たちは仕事が忙しくて櫛を手にとる暇も無いで、「昔の歌」と紹介されていますが、『万葉集』収録のものとは少し違います。
志賀(しか)の海女(あま)は藻(め)刈り塩焼き暇なみ
櫛笥の小櫛取りも見なくに
どちらも海女が忙しくて身なりなんて気を遣ってる暇も無いという悲哀を歌っています。この段全体が悲劇的な雰囲気をただよわせているのは、業平の兄行平がこのあたりに島流しになったこと、また藤原氏によって在原氏がしだいに排除され政界から遠ざけられている背景が重なっているのでしょう。
布引の滝を詠んだやり取りも、単に景色詠んだものではなく、心理を重ね合わせています。兄行平の歌は滝が流れ落ちるのを涙とみています。
次の行平の歌は滝の上で白玉を通した緒を引き抜いてバラバラーと散ったようだ、それが滝の水になったようだと大胆な見立てをしながら、最終的には「私の袖はこんなに狭いのに」と「涙」の話につなげます。どんな雄大な景色を見ても、悲しみにつながるんです。
在原氏が排除されていること、行平がかつて流されたこと、また父阿保親王のことなどが想起され、何を見ても涙につながるのです。
日が暮れて後、漁師のいさり火を見て詠んだ歌は、星か、蛍か、漁火かと美しい比喩をつかいながら、旅の哀愁、望郷の思いがただよっています。全体が沈んだ悲しげな調子です。張継の有名な詩、「楓橋夜泊」を彷彿とさせます。
月落ち烏啼きて霜天に満つ
江楓の漁火 愁眠に対す
姑蘇城外の 寒山寺
夜半鐘声 客船に到る
また、七段九段あたりの「東下り」の憂鬱な雰囲気にも通じるものがあります。
そして最後の柏の葉に書かれた歌は、海藻の「海松(みる)」を海神の神の冠の飾りと見立て、海神があなたに、惜しげもなく、こんなすばらしいものを贈ってくださったのですと詠みます。
ずっと悲劇的な感じで続いてきましたが、最後は在原氏の未来にかすかな望みをかけているのです。
龍田川
原文
むかし、男、親王(みこ)たちの逍遥したまふ所にまうでて、龍田河のほとりにて、
ちはやぶる神代も聞かず龍田河からくれなゐに水くくるとは
現代語訳
昔、男が、親王たちが遊び歩いていらっしゃる所に参上して、龍田河のほとりにて、
不思議が多かった神代の昔も、聞いたことはありません。龍田河の水がからくれない色にくくり染めになっているなんて。
解説
この歌は『古今集』にも収録されていますが、状況が少し違います。
二条の后の春宮(とうぐう)の御息所と申しける時に、御屏風に龍田川に紅葉流れたる絵(かた)を描けりけるを題にてよめる 業平朝臣
二条の后藤原高子が、皇太子の母であった時に、屏風絵を詠む形で詠ませた、ということです。『伊勢物語』4段5段あたりによると業平と高子は高子の出仕前に恋仲だったようで、そんな昔のことを思いながら、屏風絵に託す形で業平は恋の思いを詠んだのかもしれません。
しかし『伊勢物語』では屏風絵を見て、ではなく、実際に竜田川で歌を詠んだという話になっています。竜田川は奈良県生駒郡斑鳩の竜田川の山裾を流れる川で、紅葉の名所として知られます。
「ちはやぶる」は勢いが激しいの意味で、「神」または地名の「宇治」にかかる枕詞。「神代」は不思議の多かった神々の時代。「からくれなひ」は韓渡来染料による真っ赤な色。「水くくる」は、竜田川の水の上に紅葉がうつって、まるでそれがくくり染のようだと見立てます。
くくり染は、布の所々を紐でしばっておいてから染め、後で紐をほどくとジワッと複雑な模様ができるわけです。紅葉がうつりこむ竜田川の水面が、まさにその、くくり染のようだと。
竜田川の西には三室山があり、桜や紅葉の季節は見事です。百人一首に能因法師の歌が採られています。
嵐吹く三室の山のもみぢ葉は
竜田の川の錦なりけり
つひにゆく道
原文
むかし、男、わづらひて、心地死ぬべくおぼえければ、
つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのふけふとは思はざりしを
現代語訳
昔、男が病気になって、死にそうに思ったので、
最後には誰もが逝く死の道とはかねてから聞いていたが、まさか昨日今日のこととは思わなかったなあ。
解説
『伊勢物語』は元服式を終えた若者が古都・奈良でうら若い姉妹に恋をする初段にはじまり、死を予感するところで幕を閉じます。
「まさか昨日今日とは思わなかったなあ」…辞世の句らしからぬ、淡々とした歌いっぷりですが、そのことがむしろ、死に面した男の感慨をリアルに語っています。
さまざの恋に奔走し、泣き笑いにあけくれ、旅から旅に渡り歩いた男の生涯も、ここに終わります。記録によると業平は元慶(がんぎょう)4年(880年)に薨じました(『日本三代実録』)。
●『伊勢物語』でも特に有名で教科書に採られることが多い「初冠」「東下り」「芥川」など10章の音声+解説テキストを、無料でダウンロードできます。メールアドレスを入力し「ダウンロードする」ボタンを押してください。すぐにお手元のメールボックスに音声ファイルにアクセスできるurlが届きます。
声はこんな感じです。
●携帯電話のメールアドレスにはとどきません。パソコンのみの対応です。
●メールマガジンの読者サービスとして無料配布するものです。後日メールマガジン「左大臣の古典・歴史の名場面」をお送りさせていただきます。
●すべて無料で、不要な場合はいつでも解除できます。当無料ファイル送付とメルマガ配信以外にメールアドレスを使うことはありません。第三者に開示することはありません。